PM(プロパティマネージャー)に求められる最低限の不動産投資知識①
今回は、PM(プロパティマネージャー)や管理担当に求められる最低限の不動産投資知識についてお伝えしていきます。
というのも、賃貸管理を任せるオーナー様は、投資・資産運用の一環として不動産を保有しています。そのため、物件を担当するPMは最低限の不動産投資の知識を備えておかないと、オーナー様と対等に話せず、機会損失や信頼失墜につながってしまうからです。
本記事では、PMの皆様がオーナー様と会話する際に、ある程度共通認識を持てるように、基本知識をご紹介していきます。
今回押さえてほしい4つのポイント
- インカムゲインとキャピタルゲイン
- 利回り
- 法定耐用年数と減価償却
- 不動産投資のパターン
インカムゲインとキャピタルゲイン
インカムゲインとは
不動産保有中に得られるランニングの収益のことです。主に賃借人から得られる家賃収入を指します。ここから管理費用や修繕費用、借入があれば金融機関への利息の支払いを引いた残りがオーナーの利益となります。
キャピタルゲインとは
不動産の売却による利益のことです。物件の売却価格から購入時にかかった費用を差し引いた金額がキャピタルゲインとなります。
利回り
利回りとは、投資金額に対して得られる利益(リターン)の割合のことです。以下の2種類があります。
表面(グロス)利回り
年間の家賃収入を物件購入価格で割ったもの。
計算式:年間家賃収入 ÷ 物件購入価格 × 100
表面的な収益性を示すもので、経費等は考慮されていません。
実質(ネット)利回り
諸経費や税金などを考慮した実際の利回り。
計算式:(年間家賃収入 − 運営諸経費)÷(物件購入価格 + 購入時諸経費) × 100
実際の収益性を把握するにはこちらが重要です。
法定耐用年数と減価償却
オーナーとの会話で頻出するキーワードです。税金やキャッシュフロー、物件評価などに関係する重要な項目です。
法定耐用年数とは
不動産は固定資産として扱われ、使用可能な期間が国によって定められています。これが法定耐用年数です。建物構造ごとの年数は以下の通りです。
- 木造:22年
- 鉄骨:34年
- RC(鉄筋コンクリート):47年
減価償却費とは
建物の価値は年々減っていきます。この減少分を費用として計上するのが減価償却費です。
減価償却費が大きいほど利益は小さく見え、節税効果があります。
なお、法定耐用年数を超えた建物を購入した場合は、**耐用年数の20%**の期間で償却が可能です。この知識は節税や投資判断の面で極めて重要です。
不動産投資のパターン
新築アパート
主にハウスメーカーや建築会社による提案型投資。
メリット
- 融資が通りやすい
- 空室が埋まりやすい
- 維持コストが低い
- 売却しやすい
デメリット
- 利回りが低い
- 空室スタートで収益化に時間がかかる
- 新築時の家賃下落リスクがある
- 空室1室でもキャッシュフローに大きな影響
- 節税効果が少ない
中古アパート
オーナーチェンジ物件などを購入するケース。
メリット
- 高利回り
- 賃料が下がりにくい
- 節税効果あり
- 拡大戦略を取りやすい
デメリット
- 修繕コストの可能性
- 空室リスクが高い場合も
- 売却が難しい
- 管理手間が増える
新築区分マンション
ワンルームマンション投資として人気のある形態。
メリット
- 融資が通りやすい
- 少額投資でスタートできる
- 相続税対策になるケースあり
- 管理手間が少ない
デメリット
- 家賃下落リスクが大きい
- 価格が割高
- 節税効果が低い
- 利回りが低くキャッシュが残りにくい
- 空室で収入ゼロのリスク
中古区分マンション
中古の区分所有物件を取得して運用するスタイル。
メリット
- 少額で始めやすい
- 流動性が高い(売却しやすい)
- 管理手間が少ない
- 実需販売で値上がりすることもある
デメリット
- 空室=収入ゼロのリスク
- 利回りがそれほど高くない
- 節税効果は限定的
まとめ
PMがオーナーと対等に会話し、信頼を獲得するには、最低限の不動産投資知識を押さえておく必要があります。
今回ご紹介したのは、その中でも特に基本的な4項目です。
- インカムゲインとキャピタルゲイン
- 利回り(表面・実質)
- 法定耐用年数と減価償却
- 不動産投資のパターン(新築・中古、アパート・区分)
今後も引き続き、PMに求められる知識を深掘りした記事をお届けする予定です。
知識の習得を通じて、オーナーとの信頼関係を強化していきましょう。





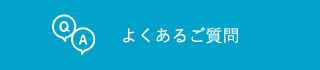
 よくあるご質問
よくあるご質問 お問い合わせ
お問い合わせ